金水敏先生の編集された『よくわかる日本語学』をご恵贈頂いた。
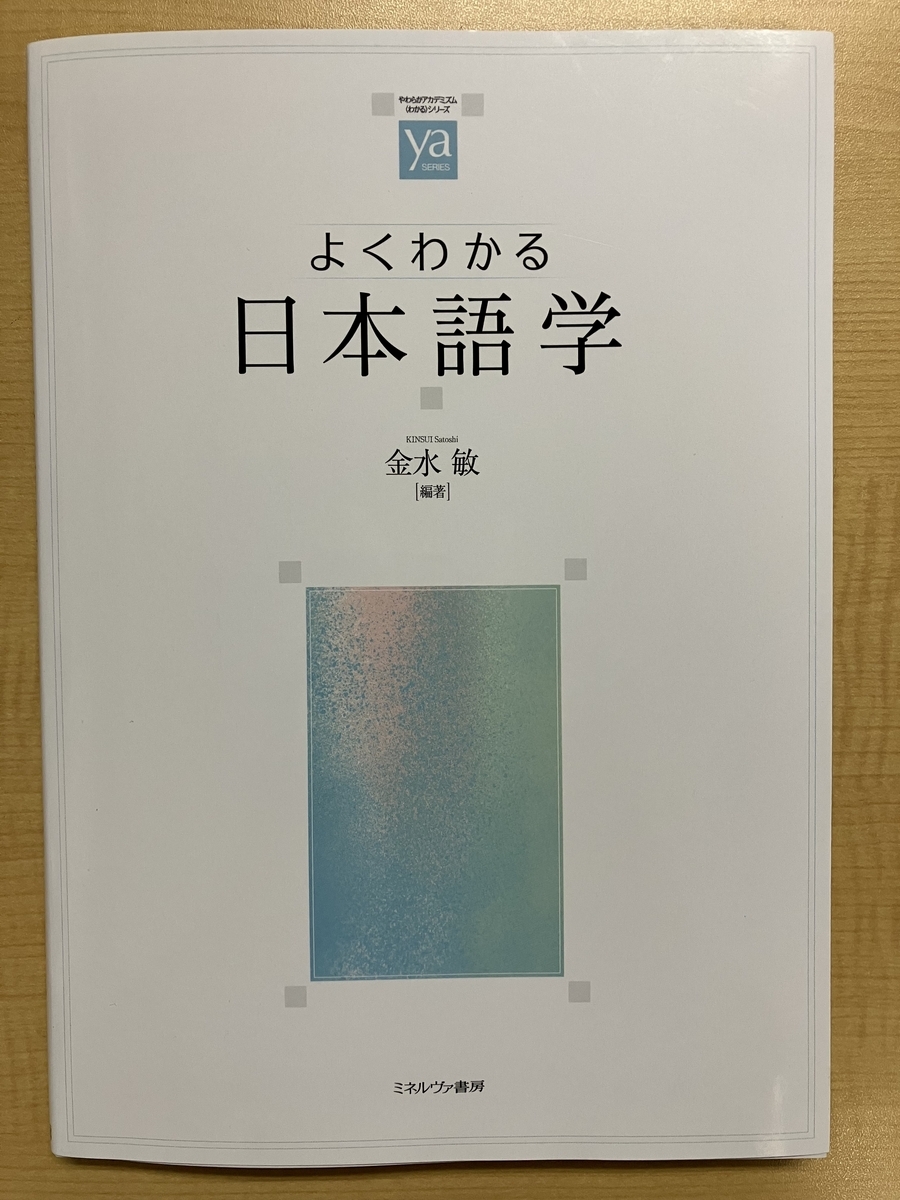
概要はサイトを参照されたい。
www.minervashobo.co.jp
以下,概要として特徴的な点と,特に音声関連の項目について紹介する(誰か他の項目を書いて!)。
本書は刊行が予告されてから高い関心を得ていた。これは私がTwitterで刊行予定を紹介したときも280ほど「いいね」が付いたことからよく分かるだろう。
金水敏(編)『よくわかる日本語学』ミネルヴァ書房 pic.twitter.com/R8ueQApXMu
— まつーらとしお (@yearman) 2024年1月31日
目次は以下のとおり(公式サイトより転載)。
1 日本語の定義
1 標準語・共通語
2 日本語が話される地域
3 日本語の話者
4 日本語の方言・日本系言語
5 日本語の近隣の言語
2 音声・音韻と表記
1 音声・音韻概説
2 母 音
3 子 音
4 音節構造(シラブル・モーラ)
5 日本語のアクセント
6 イントネーション
7 日本語の表記
3 形態論
1 動 詞
2 形容詞
3 名詞述語・形容動詞
4 語彙論
1 語 種
2 和 語
3 漢 語
4 外来語
5 混種語
6 品詞と語彙
7 オノマトペ
8 指示詞・代名詞
9 新語・流行語
5 統語論・文の意味論
1 統語論概説
2 語順とかき混ぜ・省略
3 主節と従属節
4 条件節
5 連体修飾節・準体節
6 格と格助詞
7 主題・焦点
8 動詞文
9 形容詞・形容動詞文
10 名詞述語文
11 取り立て
12 受身文
13 自発・可能
14 使役文
15 アスペクト
16 テンス
17 ムード・モダリティ
18 終助詞と文末イントネーション
19 疑問文
6 文章・文体・表現論
1 口語体と文語体
2 話し言葉と書き言葉
3 位相と位相差
4 話し言葉・書き言葉のスタイル
5 役割語とキャラクター
6 ヴァーチャル方言
7 やさしい日本語
7 言語行動・社会言語学・応用日本語学
1 敬語とポライトネス
2 命令と依頼
3 さまざまなヴァリエーション
4 言語変化
5 方言と共通語化
6 日本語教育
7 国語教育
8 日本語の歴史
1 日本語の起源・系統
2 日本語史の時代区分
3 古代日本語の資料
4 中世日本語の資料(キリシタン資料)
5 中世日本語の資料(キリシタン資料以外)
6 近世日本語の資料
7 近代・現代日本語の資料
8 音声・音韻の変化
9 表記の変化
10 形態の変化
11 語彙の変化
12 指示詞・代名詞の変化
13 ヴォイスの変化
14 テンス・アスペクトの変化
15 モダリティの変化
16 統語構造,構文の変化
17 敬語の変化
18 文章の変化
19 話し言葉の変化
20 標準語の誕生
さくいん
概要は本書のサイトに書かれているのでそちらをご覧いただくとしてここでは私が特徴的だと思った点を3つあげておく。
まず,日本語のバリエーションをかなりカバーしている。第1章「日本語の定義」に日本系言語として日系人の日本語や日本の統治時代の影響による日本語や,パラオ,小笠原,宜蘭の日本語についてそれなりにまとまった量の紹介がある。本書のターゲットとなる入門者,一般読者だとこれらの「日本語」はまずイメージすることがない点で,こういった入門書で扱われたことはとても意義があると思われる。
次に,歴史関連の項目が類書に比べかなり充実している。ひとつに日本語の起源・系統の項目が入ることはかなり珍しいと思われる。この項目は系統論・比較分析の良い入門となっている。また,音声・音韻の変化での資料が非常に充実していて,私のようにたまに授業でこれらの項目を紹介する人間には非常に助かる。
そして,打ちことばやヴァーチャル方言といったSNSを中心としたインターネットでの言葉遣いについても多く取りあげられている。このあたりの分野について研究が揃ってきたこともあるだろうが,入門書でそれなりの分量が参照文献付きで掲載されていると卒業論文やレポートの題材探しをする学生にとって助けになるように思われる。
音声関連の項目では,自然音類を中央に据えて音素を丁寧に同定する方法が紹介されている(第2章1〜3)。よくある入門書の記述(というまとめ方も雑だが)とだいぶ違うアプローチが取られている。また,パラトグラフィーを援用して母音と子音の連続性を論じるのはかなり珍しいと思われる。他に2-4で「初音の補充」として連声ないしはリエゾンと書かれる現象が紹介されている。ここで「初音を欠く音節はすわりが悪いのか」とされているが,音節初音(オンセット)を求めることは聴覚的キューの観点からの説明が有効なように思われる(Wright, Richard (2004) A review of perceptual cues and cue robustness. In: B. Hayesら (eds.) Phonetically Based Phonology.)。
ちなみに「バティストゥータ」(アルゼンチンのサッカー選手)という表記と発音について「バテストゥータやバチストゥータと発音する人はいないだろう」と書かれているが,検索すると「バチストゥータ」は見つかる。
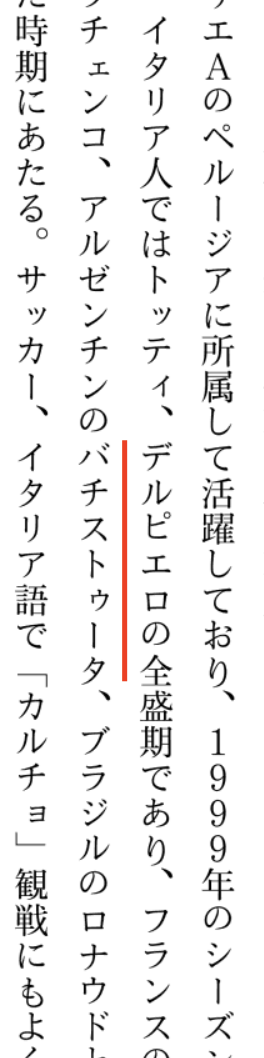
この手の有標な(外来語に特徴的に見られる音声に包含関係があるという主張もある(Ito, Junko and A. Mester (1995) Japanese phonology. In Goldsmith J. (ed.) Handbook of Phonological Theory)。
アクセント・イントネーションは,アクセントの弁別性が有無と位置にあることを丁寧に説明しているところ,およびアクセント表記について書かれているが特徴的である。また,アクセントとイントネーションの相互作用としてよくある説明はイントネーションはアクセントを上書きしないというものだったが,そうでもないという定延利之氏による研究結果を踏まえた記述があるのは有益だと思われる。
さて余談。脚注とかまえがき・あとがきを読むのがけっこう好きなのだが,軽い気持ちで脚注を紹介したらけっこうバズってしまった。わはは。
日本語学の教科書に「イッヌ」というネットスラングが市民権を得た話があって、書きっぷりが良いので見てほしい。こういうのを待ってたんだよ(誰が? pic.twitter.com/MdIBIJlGzT
— まつーらとしお (@yearman) 2024年6月17日